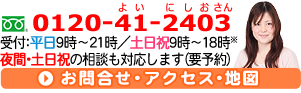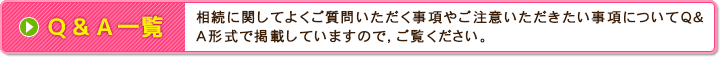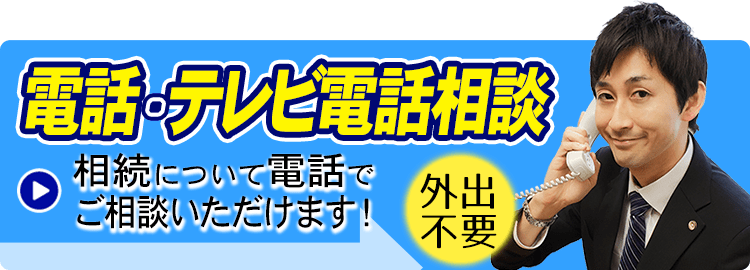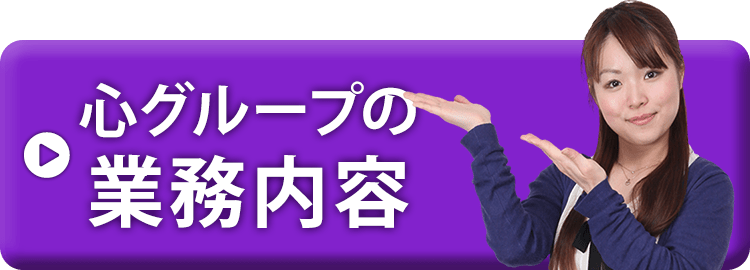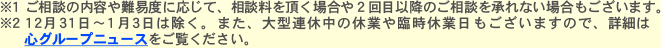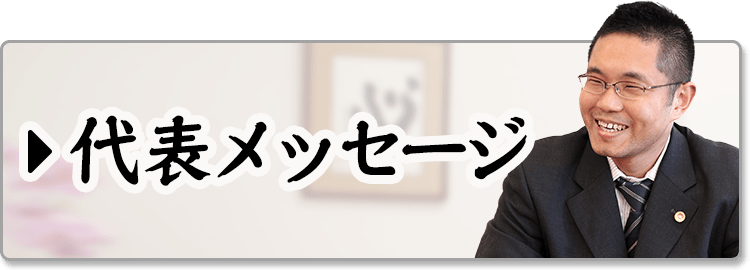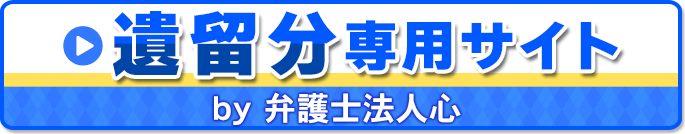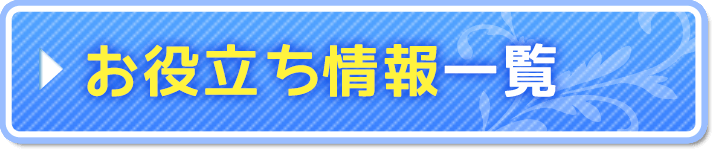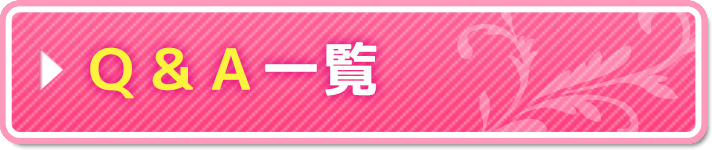相続人の一人が海外在住の場合、どのように相続手続きを進めるのか
1 基本的には国内在住の場合と同じように相続手続きを進めます
相続人の中に海外在住者がいる場合でも、日本国内での相続手続きの基本的な流れは変わりません。
被相続人がお亡くなりになられた後、戸籍謄本などを集めて相続人を確定させ、相続財産が明らかでない場合は調査をして相続財産を特定し、相続人全員で遺産分割協議を行い、その内容に基づいて各相続人が相続財産を取得します。
ただし、海外在住者がいる場合は、資料収集や相続人の間でのやり取りに時間がかかる点や、遺産分割協議書の署名・証明の形式が異なる点に注意が必要です。
2 戸籍謄本の取得
遺産分割協議を行う前提として、相続人を調査して、確定させる必要があります。
相続人の調査には、一般的に、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、および各相続人の現在の戸籍謄本を用います。
海外在住の方の場合、ご自身で戸籍謄本を取得するためには、郵送で本籍地の役場に請求する方法、あるいは、一旦日本に戻って取得する必要があります。
日本に戻ることが難しい場合には、他の相続人等にご自身の戸籍謄本の取得を依頼することになりますが、委任状が必要になる可能性もあります。
3 遺産分割協議と遺産分割協議書の作成
相続人を確定させ、相続財産の調査が済んだら、相続人全員で遺産分割協議を行う必要がありますので、一般的には海外在住の方は電話やビデオ会議、メールなどを用いて話し合いを進めることになります。
日本との時差が大きい場合には、スケジュールの調整もしっかりと行わなければなりません。
どの相続人が、どの財産を取得するかについて合意に至ったら、その合意の内容を記載した遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、基本的には相続人全員の署名と押印が必要とされます。
実務においては、国内在住の相続人は実印で押印し、印鑑証明書を添付します。
印鑑証明書は、登録した市区町村役場で取得できます。
参考リンク:木更津市・印鑑登録証明書
海外在住の相続人の方の場合、印鑑証明書がないこともありますので、別途対応が必要となります。
4 印鑑証明書がない場合
海外在住の相続人の方は、印鑑登録制度が利用できないことがあるため、一般的には印鑑証明書の代わりとして、サイン証明(署名証明書)を用います。
サイン証明は、遺産分割協議書に記載された署名が本人によるものであることを証明する書類であり、現地の在外公館などで取得することができます。
参考リンク:外務省・在外公館における証明・署名証明
遺産分割協議書に、印鑑証明書の代わりにサイン証明を添付することで、金融機関における預貯金の解約や、相続登記の際に、遺産分割協議書を用いることが可能になります。
特定財産承継遺言とは|遺贈との違いや登記、作成上の問題点について 相続放棄ができる期間はいつまでか